ブログ
2.12025
居酒屋経営は儲かる?年収は?リスクも含めた成功の秘訣を徹底解説!
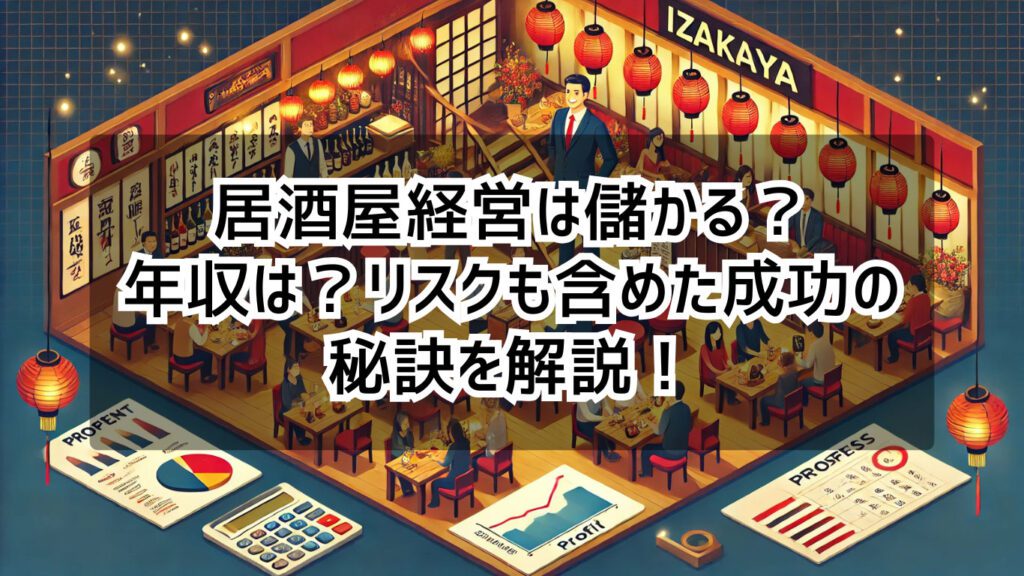
目次
- はじめに(導入)
- 居酒屋経営は儲かる?結論とその理由
- 居酒屋経営者の年収はどのくらい?
- 居酒屋の売上と利益の関係(固定費・変動費)
- 居酒屋で利益を上げるための基本原則
- 居酒屋経営で失敗する理由と対策
- 居酒屋経営のメリットとリスク
- まとめ
はじめに(導入)
居酒屋の経営で本当に儲かるのか、経営者の年収はどのくらいなのか――。こうした疑問を持つ方は多いと思います。実際、「居酒屋 経営者 年収」「居酒屋 儲かる」と検索する方は、具体的にどのくらいの利益が出るのか、どんなリスクがあるのかを知りたいはずです。
本記事では、居酒屋経営の儲かる仕組みや年収の目安、失敗例から学ぶポイントまで幅広く解説し、読者のみなさまにとって有益な情報をお届けします。独立開業を検討している方、すでに居酒屋を運営していて収益アップを目指している方は、ぜひ参考にしてみてください。
居酒屋経営は儲かる?結論とその理由
結論から言えば、居酒屋は大きく儲けられる可能性が十分にある業態です。ただし、これは「正しい立地選び」「資金管理」「人材管理」「メニュー戦略」「マーケティング」など、さまざまな要素がうまく噛み合った場合に限られると思います。コロナ禍ではたしかに大きな打撃を受けて潰れた飲食店は多かったですが、世界的案感染症の拡大という天災とも言える出来事がなければ今後も十分に設けることができるビジネスと考えます。なぜ儲かる可能性があるのか、大きく分けると以下の理由が挙げられます。
- 飲食需要の安定
多くの人にとって外食は日常的な楽しみの一つです。特に居酒屋は、仕事帰りのサラリーマンや学生、家族連れなど、幅広い層から支持されます。そして幅広い料理のラインナップを用意可能な居酒屋は様々なコンセプトを打ち出しやすい業態であるとも言えます。 - 高い粗利率が期待できる
ドリンクやフードのメニュー構成次第では、利益率を高めやすい特徴があります。ハイボール、サワー系ドリンクなどは原価が比較的低く、売価とのギャップが大きいです。 - リピーターを獲得しやすい
美味しい料理や居心地の良い雰囲気を提供できれば、一度来店してくれたお客様が繰り返し足を運んでくれる可能性が高い業態です。 - 比較的に高単価を取りやすい
ラーメンや定食屋などと異なり、1名あたりの単価で3000円~は十分すぎるほどに目指せる業態であり、その分、客数を稼げなくてもスケールする可能性がある
一方で、「必ず儲かる」わけではないことも重要な事実です。立地や経営者の経験・ノウハウ、人件費や家賃といった固定費の管理などが甘いと、思うように利益を上げられないケースも当然、珍しくありません。
居酒屋経営者の年収はどのくらい?
居酒屋オーナーの年収は、経営規模や立地、運営方針によって大きく変動します。ここでは「街の小さな居酒屋」と「複数店舗を運営する居酒屋チェーン」それぞれの目安を見ていきましょう。あくまで一例として考えてみた結果であり参考程度にしていただければと思います。
街の小さな居酒屋オーナーの場合
- 月商の目安:200万〜350万円程度(20〜40席ほどの店舗想定)
- 利益率の目安:10〜15%前後
- オーナーの年収:年300万〜600万円程度
都心の一等地であれば、家賃が高くなる一方で客単価や集客数も上がりやすいため、売上が400万円を超える繁盛店もあります。ただし、地方や家賃が安いエリアでも固定費を抑えられれば同程度の利益が出る可能性があります。小規模店のオーナーは自らホールに立つなど人件費を抑える分、利益を確保しやすい一方で、労働負荷が高くなりがちです。小規模居酒屋を生業とするのは可能だが、「良い生活ができるか」は働き方次第と言えるのではないでしょうか「好きだからやる」なら問題ないですが、時間の自由や資産形成を目指すなら別の戦略が必要かもしれません。もちろん大繁盛店をつくって適切に休みを取って十分に成功を収めているオーナーさんもいるとは思います。
複数店舗を運営する経営者の場合(成功事例)
・月商の目安(1店舗あたり):1,000万円前後
・利益率の目安:10%(ただし、業態や立地、人材コストによって当然変動する)
仮に月商1,000万円前後の店舗を5店舗経営し、平均して10%の利益率を維持できたとすると、1店舗あたりの営業利益は100万円、5店舗合計で500万円 / 月(年間6,000万円)の営業利益となります。ただし、これは本部経費やマネージャーの人件費などを控除する前の数字であり、実際の最終利益はこれよりも低くなります。また、年間6,000万円の営業利益が出ても、それがそのまま経営者の手取り収入になるわけではなく、税金・投資・設備投資・内部留保など考えたうえで配分を適切に行う必要があります。しかし、適切な経営戦略を取れば、5店舗程度のチェーンでも安定した高収入を得ることは十分可能であることがわかると思います。
居酒屋の売上と利益の関係(固定費・変動費)
居酒屋の経営で収益を上げるうえで重要なのが、売上構造とコスト構造の理解です。
- 売上:
一般的には「客単価 × 客数 × 営業日」で月商が決まります。客単価を上げる戦略(高利益の商品をメニューに載せるなど)もあれば、客数を増やす戦略(集客施策を強化する)も存在します。 - 固定費:
家賃、人件費(最低ラインのスタッフ人数分)、光熱費など、売上に関係なく毎月かかる費用。固定費を下げるほど損益分岐点が下がり、少ない売上でも黒字になりやすくなります。 - 変動費:
食材費やドリンクの原価、人件費の一部(時給アルバイトのシフトなど)、その他消耗品。売上が増えるほど一定割合で増加します。一般的な居酒屋では食材原価率を30%前後に抑え、人件費とのバランスを確保するケースが多いです。 - 利益率アップの方程式:
「売上を増やす + 固定費を抑える + 変動費を最適化する」
この3点を同時に意識することが、居酒屋経営で利益を出すための基本となります。
居酒屋で利益を上げるための基本原則
1. 集客力の強化
- 基本原則:
地域に根ざしたメディア広告やSNS、チラシなどを活用して、新規顧客の獲得に努める。ターゲット層に合わせたプロモーションを計画し、確実に情報を届ける。新規顧客をリピーターにつなげるQSCの満足度も忘れずに。 - 派生アイデア:
- 地域イベントや地元メディアとの連携によって、居酒屋自体の認知度を高める。
- オンライン予約システムや口コミサイトへの積極的な情報掲載で、利用のハードルを下げる。
2. 客単価の向上
- 基本原則:
売れ筋メニューだけでなく、高単価の商品やコースメニューを用意し、顧客の購買単価を引き上げる。季節限定メニューや特別な企画で「特別感」を演出する。 - 派生アイデア:
- 料理やドリンクの開発背景を伝えるストーリーテリングを取り入れ、付加価値を感じてもらう。
- グループ利用や宴会プランを工夫し、人数単価の向上とリピート利用を促進する。
3. コスト管理と効率化
- 基本原則:
仕入れ先の比較・交渉や、メニューの見直しによって、原価率の最適化を図る。フードロスを最小限に抑えるとともに、効率的な人員配置とオペレーションの改善を行う。 - 派生アイデア:
- 長期的な仕入れ契約やまとめ買い交渉によって、原材料コストの削減を実現する。
- ピークタイムと閑散時のデータを活用して、柔軟なシフト調整や業務フローの最適化を図る。
4. ブランド力の向上
- 基本原則:
良質なサービスと料理、そしてアットホームな雰囲気を提供することで、顧客の信頼とリピート率を高める。 - 派生アイデア:
- スタッフの接客教育や、店内の雰囲気づくりに工夫を凝らし、他店との差別化を図る。
- SNSや自社ウェブサイトで、店舗のこだわりやストーリーを定期的に発信し、ブランドイメージの強化に努める。
5. 顧客体験の向上
- 基本原則:
顧客が再訪したくなるような、快適で満足度の高い体験を提供することが重要です。 - 派生アイデア:
- 季節ごとのイベントや、限定メニューの試食会など、顧客参加型の企画を開催する。
- アンケートやフィードバックを積極的に取り入れ、顧客の意見に基づいた改善を行うことで、長期的な顧客満足度を維持する。
居酒屋経営で失敗する理由と対策
- 立地選定の失敗
- 家賃は高いが客足が期待できない、または客単価が低い地域に出店してしまう。
- 対策:出店前の市場調査と家賃相場の確認を徹底し、ターゲット層が確実にいるエリアを選ぶ。
- 資金繰り管理の甘さ
- 設備投資や内装費に予想以上のコストがかかり、運転資金不足に陥る。
- 対策:自己資本と融資のバランスを考え、余裕を持った資金計画を立てる。
- 新規顧客が獲得できない
- 広告費を適切にかけていない、人通りの悪い立地で運営してしまう等のケース。
- 対策:メディア広告を活用し、インフルエンサーなどを呼び込んでお店のPRに適切に毎月費用をかけて新規顧客を獲得する。
- リピーター獲得ができない
- メニューやサービスに独自性が少なく、店舗としての満足も低く、一度きりの来店で終わってしまう。
- 対策:人気メニューの改良、スタッフ教育、SNSやLINE公式アカウントなどでの顧客フォローを強化する。
- 過度な価格競争に巻き込まれる
- 近隣の店が値下げ合戦を始め、利益率が圧迫される。
- 対策:安さだけでなく、雰囲気やサービスを差別化要素として打ち出し、価格以外の付加価値を提供する。
居酒屋経営のメリットとリスク
メリット
- 高収益の可能性:工夫次第で原価率や客単価を調整でき、利益を上乗せしやすい。
- ブランド構築:特定の料理ジャンルやコンセプトに特化することで独自ファンを獲得しやすい。
- 安定需要:サラリーマンや学生など、繰り返し利用する層が多い。
リスク
- 初期投資の大きさ:物件取得費、内装工事費、備品購入費などまとまった資金が必要。
- 競合の激化:全国チェーンや新規参入の店舗が多く、差別化しないと埋もれる可能性が高い。
- 景気や社会情勢の影響:リーマンショックやコロナ禍など、外食産業が打撃を受ける出来事が発生するリスクが常にある。
Q&A
Q1: 居酒屋開業にはどのくらいの初期費用が必要?
小規模な居酒屋の場合、一般的には初期投資として数百万円〜1,000万円以上が必要です。具体例として、東京都内の20〜40席の店舗の場合、内装工事や備品購入、初期在庫の準備などで500〜1,200万円程度の投資が見込まれます。物件の取得条件や内装仕様、立地条件によって費用は大きく変動します。
Q2: フランチャイズと個人店、どちらが儲かる?
フランチャイズ:
ブランド力や整ったマニュアルにより、早期に安定した収益を期待できます。しかし、売上の一部としてロイヤリティ(例:売上の3〜5%)が発生するケースが多いです。
個人店:
経営の自由度が高く、オリジナリティあるメニューやサービスを展開できるため、成功すれば収益率を自社で最大化できる可能性があります。ただし、集客や運営のノウハウ、マーケティング戦略が求められるため、経営努力が必要です。
Q3: 何店舗くらい増やせば安定収益を得られる?
1店舗での成功:
一店舗で十分な収益力があれば、経営者として年収1,000万円を超えることは十分可能です。実際、東京都内の好立地の小規模居酒屋で月商200〜350万円、利益率が10〜15%の場合、オーナーの年収が300〜600万円程度になるケースが見られますが、運営や経費管理が上手くいけば十分な収益が期待できます。
2〜3店舗の場合:
もし事業拡大を検討するなら、まずは2店舗、次に3店舗と段階的な展開が理想的です。例えば、1店舗あたり月商1,000万円、利益率10%を維持できた場合、2店舗で毎月200万円、3店舗で300万円の営業利益が見込めます。ただし、3店舗以上になると、マネージャーの配置や本部経費の管理が必要になり、経営が複雑になる傾向があります。
まとめ
居酒屋経営は、正しい戦略や地道な努力を続けることで儲かる業態になり得ます。特に家賃、人件費、食材原価などのコスト構造をうまく管理し、リピーターを確保する仕掛けを作れれば、経営者の年収も大きく伸びるでしょう。
一方で、立地選びや資金繰りを誤ったり、競合との差別化ができなかったりすると、失敗に陥るリスクもあります。メリットだけでなくデメリットを把握したうえで、資金計画やマーケティングにしっかり注力してください。
もし「居酒屋を始めたいけど具体的な流れがわからない」「現在の店舗をもっと利益体質にしたい」などのお悩みがあれば、専門家のアドバイスや他業態・他社事例の研究を取り入れるのも一つの手です。着実に準備を進めれば、居酒屋経営で成功をつかむチャンスは十分あります。集客やWEB活用にお困りのことがあればぜひ私にお問い合わせください。
大学生の頃からウェブサイト作成やアフィリエイトに触れ、自然とSEOやWebマーケティングの知識を身につけてきました。その後、当時100店舗以上の飲食店を運営する企業に入社しグルメメディアの管理・運用やリスティング広告の運用をする機会を得て、飲食店のオンライン集客業務の経験を積んでまいりました。その後さら後、当時創業して間もない外食企業にヘッドハントされ転職。1店舗→80店舗を超え規模までWebや広告まわりの責任者として務めてきました。グルメインフルエンサーとしての活動も行い、インフルエンサーマーケティングの知見を活かした販促企画にも力を入れてきました。常に「飲食店がより多くの方に選ばれるように」という思いを大切に、現場と二人三脚で取り組んでいます。より良いサービスを提供するためにこれからも勉強と実践を重ねていく所存です。









